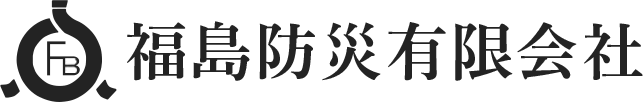毎年1月26日は,「文化財防火デー」です。
文化財防火デーの制定は,昭和24年1月26日に,現存する世界最古の木造建造物である法隆寺(奈良県)の金堂が炎上し,壁画が焼損したことに基づいています。
火災など災害による文化財保護の危機を深く憂慮する世論が高まり,翌昭和25年に文化財保護の統括的法律として文化財保護法が制定されました。
弊社は創業以来県内外の多くの文化財の設計や施工などで携わって参りました。
今年度は柳津町にある「奥之院弁天堂」、会津美里町にある「福生寺観音堂」、「法用寺観音堂」の文化財防火デーの訓練に立会いました。
通報訓練、重要文化財の搬出訓練、放水銃を使用した消火訓練、消防団によるポンプ車を使用した消火訓練などを行いました。
文化財の消火活動というのは消防署だけでなく消防団の方々等の地域の皆様のご協力のもと成り立ちます。弊社では火災発生時、感知器と連動して屋外サイレンを鳴らすことで近隣の方々にも火災を知らせる設計をしております。
復元した建物の為文化財ではありませんでしたが、首里城があれだけ大規模に焼けてしまったのも初動の遅さが原因の一つとして挙げられています。もちろん昔の建物は木造で風通しが良い為、火の回りが想定より早かったかもしれませんが、火災というのはとにかく早い段階で抑えることが被害を最小限にする方法の為、地理をよく知っている地元の消防団にご協力いただき、可能なら消防車が来る前に消すことが出来れば被害を最小限に抑えることができます。
過去を教訓に文化財防火デーが制定されましたが、貴重な文化財を後世へ残していくため訓練を行うことは大変重要だと思います。
奥之院弁天堂消火訓練の様子

福生寺観音堂消火訓練の様子

法用寺観音堂消火訓練の様子(写真は三重塔)

弊社では文化財に限らず点検のご契約をいただいているお客様へ無償で訓練支援を行っております。
消防署も地域の建物全てを把握できない為、建物に危険物などを保管している場合は消防車が来た際に防火管理者が建物の説明をしなければなりません。燃えている物によっては水をかけてはダメな場合もあるため、火災を想定して訓練を行いましょう。